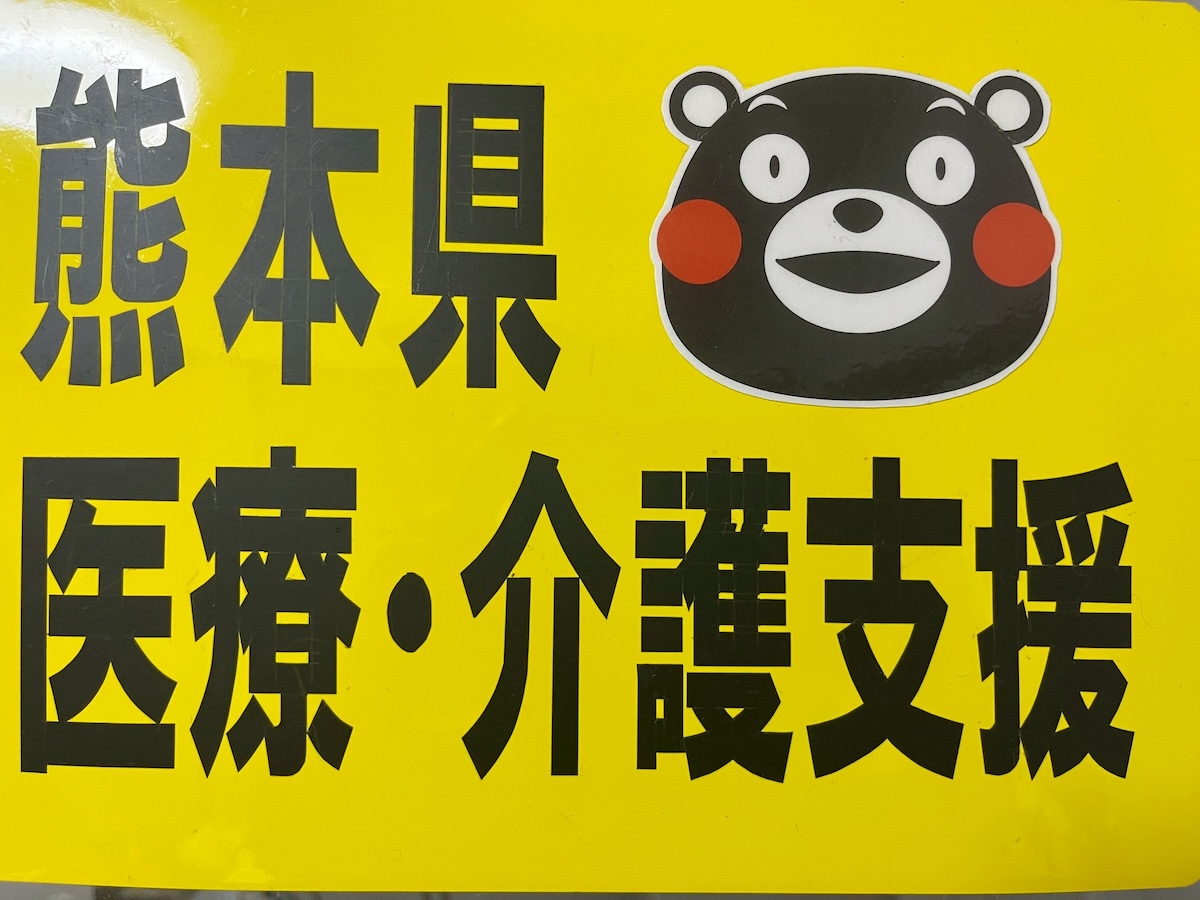ロードバイクでサイクリングをしていると、流れる景色に魂を奪われそうになる瞬間がある。真っ青な水平線に浮かぶ白い入道雲。西へと傾いていく太陽の光をキラキラと小さな星のように無限に反射する大海原。ロードバイクを止めて、もっとしっかり、じっくり見ようとするとその憧れにも似た景色はたちどころに消えて失くなる。流れ去って行く一瞬の景色だからこそ、憧憬が生まれるのだ。
ところで、私たちは、流れる時間の中に生きている。流れ去って行く時の中にいるからこそ、どうしても忘れようにも忘れられない一瞬の景色があるのだろう。そんなことを考えているうちに、ある光景を思い出していた。
まずは、昨年1月のことから書き始めたい。
昨年の元旦、能登半島を巨大地震が襲った。正月明けすぐに熊本県医師会からJMAT活動募集の案内状がFAXで届いていた。JMAT活動として能登半島へ行くことの出来る日付けを記入し、帯同する予定の人員の職種と名前も記載するようにしてあった。全ての日付に丸印を入れた。
1回目のJMAT活動は1月中旬にかけての一週間だった。自院看護師2名、嘱託医を務める障害者施設の看護師1名(施設の希望者の中から施設長が私に預けてくれた)、凍結や積雪した道路を走るのが不安でもあり自院運転手1名と私の計5名で参加した。天草を出発した翌日、福岡空港から小松空港へ飛んだ。小松空港からはレンタカーに乗り、金沢の石川県庁でJMAT活動の登録をした上で、JMAT能登中部の本部のある七尾市へと向かった。県庁11階にあったJMAT本部は人でごった返していた。能登半島へ向かう途中の道路には積雪はなかった。救急車やパトカー、救援物資を運ぶトラック、救護活動を行うのだろう自衛隊員を荷台に満載した自衛隊トラックなどで混雑していた。全て、他府県のナンバープレートだった。想像を上回る勢いで救援活動が始まっていた。
その時のJMATのメイン活動は、あちらこちらに緊急的に作られた避難所での健康管理だった。まだコロナ禍の最中でもあり、インフルエンザも同時流行していた。活動前後の朝と夕方には、JMAT能登中部の調整本部に集合し、DMATとの調整や役割分担の確認、明日の予定の申し合わせ、活動の引き継ぎ、さまざまの課題についての意見交換などが1~2時間にわたって行われていた。地震の被害の大きさを改めて感じさせられた。中途半端な災害ではないのだ。皆が興奮し、時には殺気立ち、中には立ったままずっと喋り続ける方もおられた。場違いなところに来てしまった自分とは違い、皆若く元気で使命感に燃えているのだ。カッコつけの中途半端な覚悟で来たらいけなかったのではと後悔している自分がいた。
活動3〜4日目の夜の会議だったと思う。外はブリザードとなっていた。車のヘッドライトに照らされた吹雪の景色を覚えている。その時の会議は、志賀町立富来病院の3階の会議室で行われた。能登半島中部のJMAT本部とは,ZOOMで繋がっていた。志賀町富来地区にある介護医療院には、療養介護が必要な介護老人患者60名以上が十分とは言えない環境で放置されているかもしれないという情報が提供された。DMATチーム、JMATチームともに、何度訪問しても施設へ入ることを頑なに拒否されているというのだ。違和感を持った。
翌日の朝数か所の避難所を訪問したあと、恐る恐る、昨日話題になっていたその施設を訪問してみた。玄関ブザーを鳴らし要件を告げ、粉雪の舞う中、施設の玄関前駐車場で立ったまま待っていると、しばらくして、白いコットンジャンパーを着た70歳前後と思しき男性が現われた。施設の院長だと名乗りながら厳しい顔をしておられる。JMAT活動として医療・看護の支援をしたいと申し出た。すると、必要ないから帰ってくれと云われる。もう一度、提案した。施設の方針は必ず守った上で行うので、是非、医療・看護の支援をさせて欲しいと。すると、院長の表情には微妙な変化があった。しばらくの沈黙の後、施設の方針及び自分の診療の方針の下で必ず行うのかを再び確認された。それに肯くと、ではお願いしたいと云われる。
こうして、我々5名のチームは、DMAT、JMATチーム合わせた中で、初めてその介護医療院の施設へ入場を許されたチームとなった。
一階部分がクリニックの外来や検査、リハビリ部門。二階が介護医療院の入院施設というのが、この施設の本来の姿であった。地震で二階のあちらこちらの天井が崩落し、スプリンクラーも作動して水びたしとなり、二階部分の入院設備は全て使えなくなっていた。被災当日は津波警報が出たため、60数名の全入院患者を院長も含めた4、5人の職員で、車イスや毛布に寝かしたまま引きずりながら病院建物裏の高台に移したとのこと。寒さと戦うために、高台の駐車場で皆で毛布を被って固く集まり円陣を組んで数時間を過ごした。夜になっても津波警報は出たままだったが、このままだと低体温症になる危険があると判断。再び、車イスや毛布を利用して全患者を施設一階(受付、待合室、廊下、外来診察室、各種検査室などとにかく全ての部分)へ移した。その頃には、当日非番となっていた施設職員も続々と応援に駆けつけ(職員の自宅も被災していたのだ)、皆で余震の続く中、不安な夜を一緒に過ごしたとのことだった。
数日後、DMATチームが訪問した頃には、停電も復旧し、暖房設備も作動していた。断水は続いていたが食事の手配はあちこち走り回り何とか出来るようになっていた。施設には更に、近くの有床のクリニックや高齢者施設、輪島市の高齢者施設などからも療養の必要な患者を依頼され、併せて70〜80人の患者の療養管理をしていた(みなし福祉避難所としての役割りもしていたのだ)。DMATチームはその惨状をみて、入院患者に災害関連死となるリスクを感じたのであろう。全患者を車で2〜3時間かけて、金沢市やその周辺の医療施設へ転院させることを提案したのだという。院長は、それを敢然と拒絶した。一応、職員も全員無事で、必要最小限の医療・介護は行えているのだから、移送する必要はないと。移送すればさらに患者へのダメージが大きくなると考えたのだという。それ以来、その施設はDMAT・JMAT活動の中で手を付けられることもなく、ある意味置き去りにされていた施設だったのだ。正に戦いの最前線で孤軍奮闘の状態となっていた。
我々がその施設に入り現状を把握した日の夜、その件をJMAT調整会議で報告した。翌日再び我々のチームはその施設を朝から訪問するようにと、JMAT調整本部から指示があった。翌日は朝からその施設の医療・看護・介護支援活動に入った。午後になると、DMAT本部の幹部の方々や、他県の保健所長の方々の訪問があった。皆、ただ黙って現状把握に努めておられる様子だった。
私のJMAT活動は、その後もその施設との繋がりを深めて行った。1月の下旬には、私の妻のチームも医療支援に赴いて、その施設で震災後初めてとなる入浴介護の医療的サポートをすることができた(施設の入浴設備は壊れていたため富山県からボランティアでの訪問入浴サービス車が来てくれていた)。
2月には、私と天草,御所浦の高齢者施設(過去にコロナクラスターで医療支援に入った施設であり信頼関係を構築できていた)の看護師1名、障害者施設の看護師1名と介護士1名の4名のチームとした。施設を3泊4日で訪問し、医療・介護支援活動を行った。その頃にはすでに、DPATのチームやJRAT,DWATなどのチームも支援に訪れていた。他府県から派遣された保健師の方々も施設に泊まり込みで活動されていた。二度と会うこともないであろう保健師さんたちといろんなおしゃべりをした。厳しい環境の中でもひとときの楽しい時間となった。
帯同した介護士は、毎日の午後、施設一階のクリニック待合室部分に入院療養中の患者さん多数を集め、レクリエーション活動を行った。手遊び体操として「むすんで開いて」「お寺の花子さん」「ミカンの花咲く丘」など5、6曲。足踏み体操として「カモメの水兵さん」「365日のテーマ」「手をたたきましょう」などを5、6曲。自分で作ったステージ衣装を身にまとい、歌や踊りを披露していた。アルコールはないままでも入院患者さんや施設職員は、皆で手をたたいたり歌ったり一緒に踊ったりして盛り上がっていた。
3回目は3月下旬で3泊4日のスケジュール。すでに熊本県のJMAT活動は終了しており、石川県庁でのチェックインは不要だった。県医師会からは、熊本県医師会のプラカードは持って入ってよいとのお墨付きをもらっていた。くまモンの絵柄の入ったプラカードを持っていった。それがないと、警察による検問所もある能登半島の深部には簡単には入れないのだ。熊本地震の時のJMAT活動でいただいた、熊本県医師会の文字の入った腕章も持っていった。私と障害者施設の介護士2名の3人で訪問した。今回も介護士は前回を上回る周到な準備の下、毎日の午後、レクリエーション活動を行った。
“非日常”の中で、“日常”を求めて働く人と、“日常”を飛び出して“非日常”に入り込む人とが同じ場所で働いている。それは不思議な光景だった。
最終日の夕方、全ての支援活動を終了し、天草へ戻ろうとレンタカーに乗り、施設職員(かなりの数の職員も被災され、あちこちの避難所から通勤をされていた)の温かい笑顔、「また来てねー」の声に見送られながら施設を後にした。施設を出てすぐの国道沿いに、既に通常営業となったスーパーがあった。二人の介護士が家族へのお土産に「加賀のお麩」を買いたいとのことでスーパー駐車場に車を停め、二人の買物が済むのを待っていた時だ。
買物袋を下げ車へ戻ろうとする二人めがけて、一人の60代くらいの片脚を少しだけ引きずった女性が何かを叫びながら走って追いかけてきた。そして彼女は自分の持っていた、「お菓子」のような品物を二人に押し付けるようにして渡した。そして二人の介護士に抱きつかんばかりにしている。そのうち、その60代女性と一緒に二人の介護士も泣き出した。
私も車を降り、その三人に近付いた。その女性はたまたまその日は仕事が休みでスーパーへ買い物に来ていた、私にも見覚えのある施設の看護師長さんだったのだ。二人の介護士がスーパーに居るのをたまたま見付け、自分のバッグなどをそのまま放り出し、スーパーの棚にあったお菓子を掴んでレジも通さずに追いかけてきたのだ。別れを惜しみ、その場で立ったまま抱き合うようにして泣く三人の女性。何とも表現しようのない光景だった。たぶん一生忘れられない景色になったと思う。
DMATチームは、災害で生命のリスクにさらされた人々を、取りあえず安全な場所へと移送したり、緊急時にはその場で救命することがその使命なのだろう。従って、能登半島地震の直後、その施設の入院患者さんを県内の被災していない施設へ転送しようとしたことは正しい判断だったと思う。しかし、その時点ではすでに何とか療養・介護の維持が出来る体制になっていると考えいた施設の院長が、その転送の提案を拒否したことはもっと凄い英断だったと思えるのだ。自分でその後の全ての責任を引き受けられるかどうかの葛藤もあったと思う。しかもその院長は法人に雇用された雇われの院長だ。私なら、全ての患者さんをDMATチームに託し、さっさと自分の地元(院長は東京出身だった)へと逃げ帰っていたに違いない。
入院している要介護の高齢者の患者さんたちにとっては、自分の顔馴染みの施設職員が、そばにいてくれることが最も安心なことだったのではと思えるのだ。
ベストセラーになった「ストレス脳」を書いたスウェーデンの精神科医、アンデッシュ・ハンセンは、ハーバード大学で80年以上にわたり現在でも研究されている課題 「人間にとって最も幸せなことはなにか?」について言及している。それは、お金や権力、社会的地位を得ることではなかった。自分の家族や友人、自分の周りにいる知った人たちと、いかに良い時間を共有し共感していくか、なのだという。今回のケースに当てはめてみれば、入院患者と施設職員の関係ではあるかもしれないが、自分のことを知っている人と、たとえ地震被害でとても辛い時間であったとしても、ともかく一緒にいて同じ時間を過ごすということが、大切なことだったのではないか。
被災直後の人たちにとっては、自分たちが見捨てられていないと感じる必要がある。それは、「被災した施設の職員」においても同じことである。無傷な外部から人が来た、ということが当初は大切なのではないか。そのうえで、他府県から応援に来た人たちが、被災した救援者(施設職員)の心を支える「救援者の救援者」になれれば、と思うのだ。
災害時の医療・看護・介護の支援活動は、様々な要因が複雑に絡まり合い、正解を導き出すのはなかなか難しい。これからも考え続けていかねばならないことだと思っている。
流れ去って行く時の中に残る印象的な景色を思い出しながら書いてみた。
掲載情報
| 掲載誌 | 天草医報 |
|---|---|
| 掲載号 | 2025年7月号 |
| 発行ナンバー |