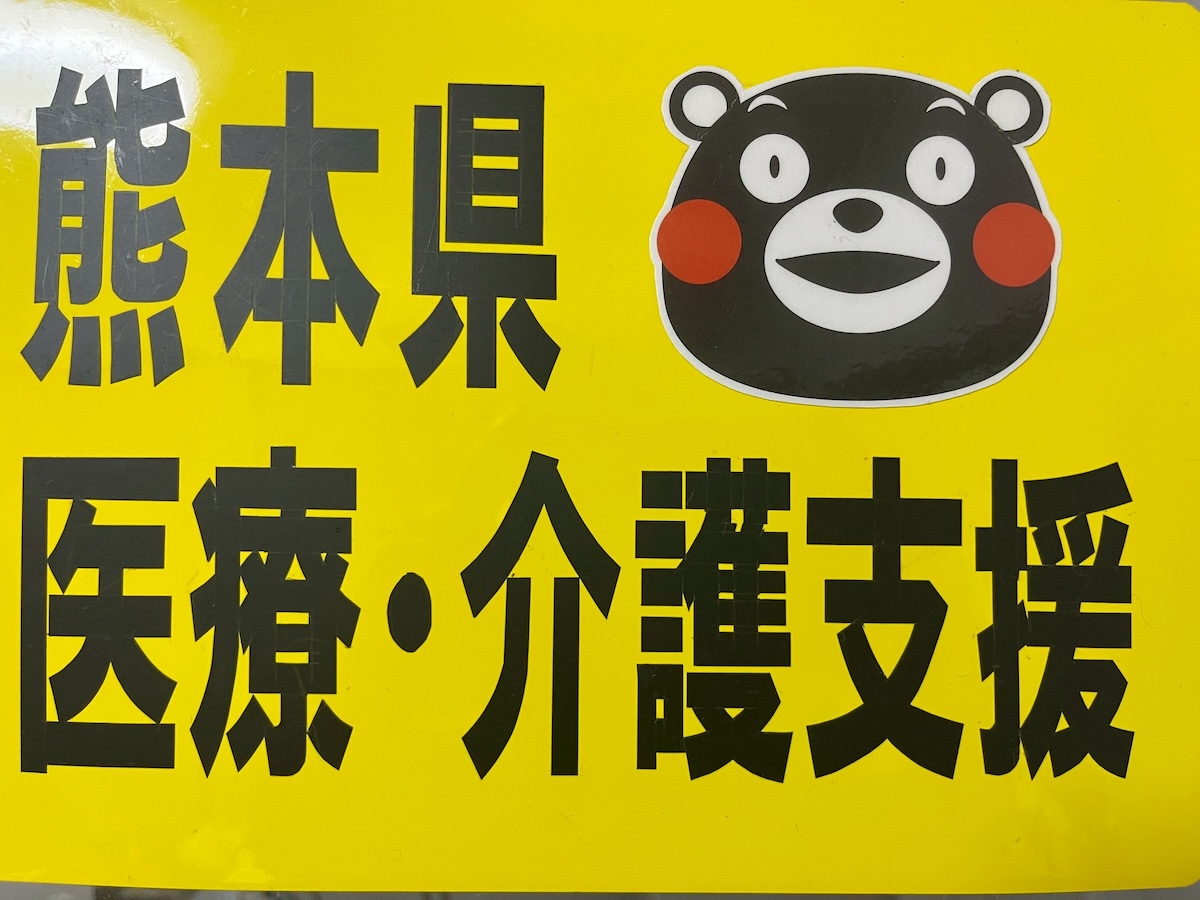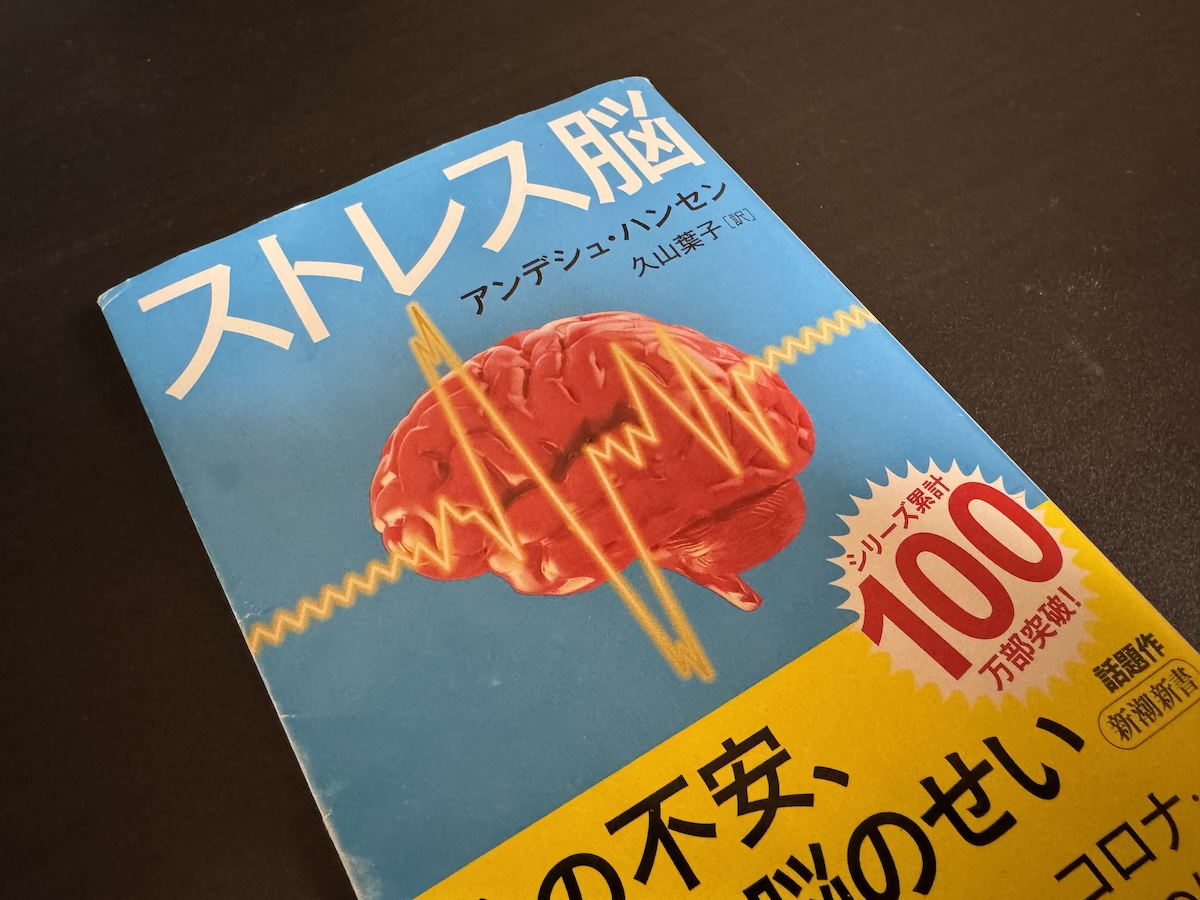天草市佐伊津町にある特別養護老人ホームの嘱託医を引き受けてから、13年が経った。最初の頃は、それまでの施設の通例に倣って、入所者に発熱があるとすぐに近隣の療養病床を持つ病院や天草市の中核病院へ入院治療の相談をしていた。その結果、病院と施設との入退院を繰り返したり、そのまま転送先での病院死となられていた。
嘱託医となり数年が経過した頃であったろうか。施設に入所されている方々の発熱の原因は、そのほとんどが、誤嚥性肺炎によるものだということに気付いた。誤嚥性肺炎は、ただでさえ誤嚥しやすくなってしまった高齢者が誤嚥をしても、咳込みが起こらないことにより起こりやすい。誤嚥をしやすくなるのは、喉頭蓋を中心とした咽喉頭、気管周辺の器官の動きに齟齬が生じるためであり、その司令塔は延髄にある。また、異物が気道に入ってしまった時に起きるはずの咳嗽反射の中枢も同じく延髄である。血液酸素飽和度を正常に保つための呼吸数や呼吸の深さを自動的に調整する呼吸中枢もやはり橋から延髄にある。橋や延髄の存在する脳幹部を栄養し酸素を送り込む血管は、脳底動脈や椎骨動脈であり、その複雑なルートやバイパスのおかげで虚血や出血を起こしにくいとも言われている。人生の最後まで無事に機能するべく設計されているのだ。
「誤嚥性肺炎」は、お釈迦様の云われた人生の四苦「生老病死」の文字の順番のまま「生」きて「老」い「病」を得て「死」に至るの、まさに「病」にあたるものと思われる。
施設入所の方で、90歳前後となられ、ほぼ寝たきり状態となっておられる方に誤嚥性肺炎が合併したと思われると、施設内でとりあえず肺炎治療を行う。その後すぐに御家族とのムンテラの機会を設ける。今書いたようなことを説明した上で、再び誤嚥性肺炎と思われる状態となった時には、より濃厚な医学的管理の出来る病院への転送を希望されるか、または、このまま施設内で出来る範囲での治療をして「お看とり」となる可能性もあることを告げる。その上で、御自分では判断の出来なくなった御本人に代わり、御家族に、病院転送か施設内治療でいくのかを判断していただくことにしている。
結果そのほとんどが、施設での出来得る範囲での治療を望まれる。というか病院への転送を望まれるケースは、最初から施設には入所されていないものと思われる。
今年春先のことだった。すでに5〜6回の誤嚥性肺炎の治療をしてきた方で、それまでに2〜3回のムンテラを繰り返し行なっていた方のケースだ。施設内で出来得る範囲での治療を希望されていた。誤嚥性肺炎の治療は、再発するたびにその治療に対する抵抗性が増していくのを感じる。
今回こそは、看取りになるかと思われる時だった。その入所者の方の娘さんが、施設に毎日泊まり込むようになられたのだ。(コロナ禍も終わり、それができるようになっていた。)元看護師でもあられた娘さんの目には、施設での看護・医療レベルが、満足行くものとは見えなかったのであろう。泊まり込むようになられてから、施設看護師への注文や質問が増えていった。1日の点滴の量について相当であるかの相談、酸素投与量や喀痰吸引の頻度についての疑問点、上半身挙上の角度は適切かなど。御自分でも、足マッサージなどもしておられたようだった。
そうした中、普段夜間は、看護師は呼び出し体制(オンコール)となっているのだが、その娘さんが泊まり込むようになられてからは、施設看護師も泊まり込み体制へとなって行った。
施設長から、再度、その方の御家族と話し合ってもらえないかとの相談を受けた。病院へ紹介してもらえないだろうかとの相談だった。
病院と老人保健施設(介護老人保健施設)、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の役割りやシステムの違い、医療と介護の占める割合が異なることなどについても大方説明した上で、当施設で出来る医療的介入ではご家族の希望には追いつかないであろうこと、希望に沿うことが出来ずに申し訳ないことなどを話した。その上で、今以上の医療的介入を望まれるのであれば病院へ転送をした方が良いとの判断を何度もすすめるのだが、頑なにそれを拒否される。病院に入院させてしまえば、自分の泊まり込み介護も出来なくなるし、今の施設での看取りも十分覚悟しており納得していると云われるのだ。
施設看護師も、相当ストレスになっていたのだろう。施設を退職したいとの希望が出ているとの話も聞こえてきた。私自身、嘱託医を辞退することも頭をよぎった。自分の能力の限界を感じたためだ。そうこうしていた約1週間くらいあと、その方は安らかに息を引き取られた。娘さんにも、見取りのあとには、ようやく笑顔が見えた。
施設看護師たちも、言い方は悪いが肩の荷が下りた様子だった。
今回のこのようなケースは、内容や程度は違えど、どの施設でも起こり得ること、起きていることではないだろうか。どうすれば、もっと皆が悩まずにすんだのだろうか。暗澹とした日々を過ごさずにすんだのだろうか。こう考えあぐねていた時、一つの小説の冒頭が頭の中に浮かんで来た。夏目漱石の「草枕」である。
「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、書が出来る。~」
この世で仕事として医療に携わり何とか自分の生活を維持しているのである。どんなことも、この世で生きている証と受け止め、ありがたいと思わねばならないのだと、自分に言い聞かせた。
掲載情報
| 掲載誌 | 天草医報 |
|---|---|
| 掲載号 | 2025年7月号 |
| 発行ナンバー |